(3)「蠢く触手」を読む
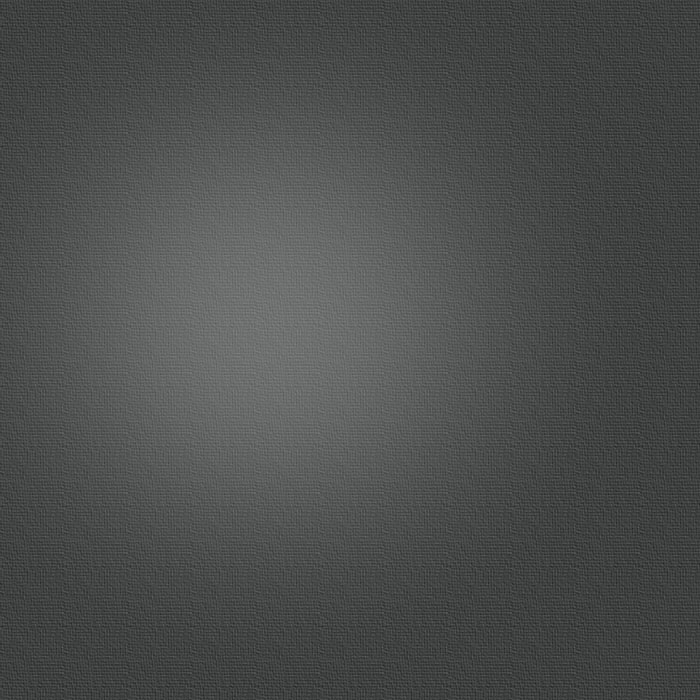
遅蒔きながら江戸川乱歩作とかつていわれた「蠢く触手」(春陽堂文庫)を読んだ。これは1997年に同文庫に収録されたもので、珍しい作品をよくぞ復刻してくれる有り難い出版社である。しかし買っては見たもののいままでどういうわけか本棚にほうり出していた。そのわけの一つは一応初版では江戸川乱歩作、という名前ではでたものの、実は岡戸武平の代作であるからである。その書誌学的解説は山前譲氏が文庫の解説でていねいにしてくれているので、ここでくり返す愚はおこなわないことにしよう。
しかし本文を一目みてみれば、これは乱歩の作品ではないなということはだれでも容易にわかるはずだ。乱歩特有の、ねっとりしたまとわりつくような語り口はみじんもなく、むしろ新聞社を舞台にしたこの作品の文体はきびきびしてかえって読みやすいくらいである。これではあまりにも乱歩の名前を名乗っているわりには乱歩らしくない、と手がのびなかった理由の一つがここにある。確かに一部には乱歩の代表作「人間椅子」を引き合いにだしてはいる。乱歩自身もこの作品がお気に入りだったらしく、何回か他の作品でこのトリックを使用したり、登場人物の探偵小説家の代表作にしてやったりしている。おなじようなことをしているというのもほほえましいが、できればもうちょっと文体を似せてほしかったものだ。それに最後の最後になって明智小五郎が登場して事件を解決するが、これもスキー帽に青眼鏡というさえないいでたちで、かなりがっかりさせられる。
船のなかでのバラバラ殺人の映画など乱歩で馴れた読者感覚から見ても少々やりすぎと思われるような趣向がこらされているのは、どうにか乱歩にちかづけようという努力だと思われるのだが、しかし乱歩が乱歩たる所以は、単に血飛沫をあげればいい、死体を弄べばいいというものではなかろう。まったくそのような趣向のない作品、それこそ「怪人二十面相」であっても乱歩作品には乱歩らしさと言うものが感じられるのである。
では乱歩らしさとは何だろうか?もちろん残虐趣味という人もいるだろうし、回顧趣味という人もいるかもしれない。彼は戦前において「なつかしの大乱歩」と広告で銘打たれたそうだから。しかしそれでもまだ足りない。その答えは私もまだ見つかっていない。ただ羅列的にくりだしてみれば、幼児性、胎内趣味、幽玄、夢、おとぎ話といった言葉が思い付く。